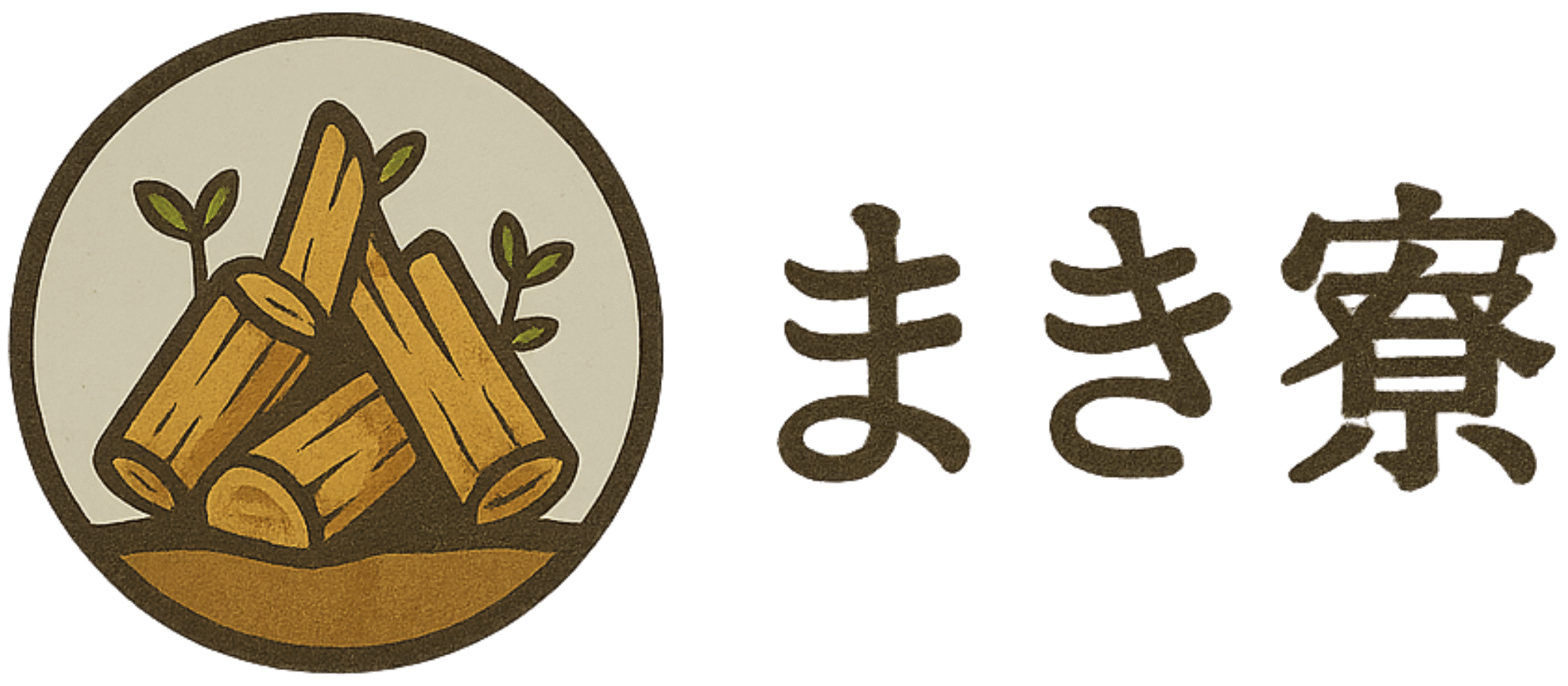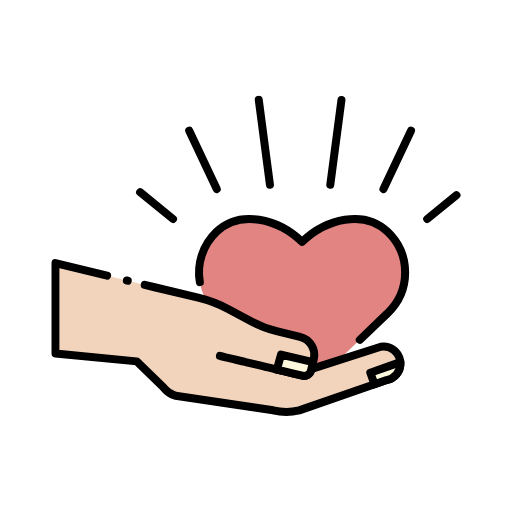子どもの自殺が後を絶たない。いじめや学業のつまずき、家庭の悩みなど要因はさまざまだが、少子化が進む中で若い命が失われる現実はあまりに痛ましい。
特に夏休み明けは、自殺が増える時期とされる。今月10日からは自殺予防週間も始まった。この機会に社会全体で危機感を共有し、実効性のある対策を進めたい。
小中高生の自殺は2024年に過去最多の529人に達した。全年代で自殺者数が減少傾向にあるにもかかわらず、子どもの数は22年以降、年間500人を超える高水準が続いている。「いのち支える自殺対策推進センター」によれば、自分を傷つけて救急搬送された6~18歳は2022年に3400件を超え、5年前の1.8倍に膨れ上がった。深刻な事態と言わざるを得ない。
背景にはSNSの影響もある。ネット上で仲間外れや中傷を受け、心に傷を負う子は少なくない。さらに市販薬の過剰摂取など危険な手段をSNSで知り、自殺に結びつく例も増えている。
文部科学省は教員向けに自殺防止の新たな指針を作成する方針だ。兆候を示し、医療機関との連携方法を明確にするという。心の病が背景にある場合、教員だけでの対応には限界がある。専門家の知見を取り入れ、現場で本当に役立つものにしなければならない。
ただ、指針だけでは足りない。普段から家庭や学校以外に、安心して本音を話せる居場所を増やすことが重要だ。地域のサークルや図書館、匿名で悩みを相談できるネット上の交流サイトなど、多様な「隠れ家」が子どもを支える。世界が広がり、つらさが和らぐきっかけになるだろう。
子どもたちが孤立せず、安心して生きられる社会をどう築くか。大人一人ひとりに問われている。